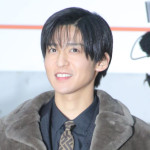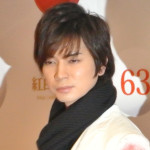甲州街道・小原宿を歩く/内田晃「ゆるゆる『歩き旅』のススメ!
徳川幕府が整備させた五街道の一つで、江戸から甲府(山梨県)を経て下諏訪(長野県)に至る甲州街道。日本橋から数えて9番目の宿場が、神奈川県相模原市の小原(おばら)宿だ。県内唯一となる当時の本陣が見学できると聞き、やって来た。
最寄駅はJR中央本線相模湖駅。こ方面へ20分も歩けば小原宿に着くが、せっかくなので相模湖に寄り道する。1947年に相模川をせき止めて造られたダム湖で遊覧船や貸しボート、釣りなどが楽しめる。
湖畔のベンチに座り、のんびりと景色を楽しんだら相模湖大橋で対岸へ。最初のT字路を左折し、急坂を上り下りするとつり橋に出た。弁天橋といい、対岸の巨岩の上に弁天堂がある。
説明板によると日本古来の宇賀神と七福神で有名な弁財天を習合した宇賀弁財天が祀られ、御神像は弘法大師が刻んだという。現在御神像は黒漆塗りの厨子に納められ、近くの善勝寺に安置されている。普段は非公開だが、巳年に御開帳するとも。奇しくも今年は巳年! もしやを期待して足を延ばしてみる。
「御開帳は5月3日から6日の予定です。せっかくだから厨子だけでもご覧になりますか?」とご住職。突然の訪問にもかかわらず、本堂内を案内してくれた。
厨子は高さ50センチほど。御神像の写真を見せてもらうと蛇体の老翁がガマガエルの背に乗っている。厨子は地元出身の武士が奉納したもので、奉納後に大出世したそうだ。改めて、御神像を拝むとご住職がほほえんだ。
善勝寺から国道20号を20分ほど歩くと小原宿本陣に到着だ。本陣は参勤交代の大名や公家などが宿泊する場所をいい、小原宿では名主の清水家が使われた。宿場の東側には難所の小仏峠があり、峠越えの前後に英気を養ったことだろう。
表門をくぐると入母屋造りの重厚な主屋が正面にそびえていて圧倒された。総面積91坪。内部は西側が本陣、東側が家人の居住部に区切られている。本陣の玄関は瓦屋根の庇や式台があるのに対して、家人用はただの引き戸といった具合に、部屋の造りや調度品、トイレまでことごとく違う。江戸期の身分制度の厳しさを痛感した。
本陣から相模湖駅へ戻る国道20号沿いには出桁造りの古民家が並んでいた。これらは明治期の大火後に再建されたものだが、旅籠時代の屋号を記した表札が掲げてあり、宿場の趣が感じられる。街道を歩く旅人気分をしばし楽しんだ。
内田晃(うちだ・あきら):自転車での日本一周を機に旅行記者を志す。街道、古道、巡礼道、路地裏など〝歩き取材〟を得意とする。