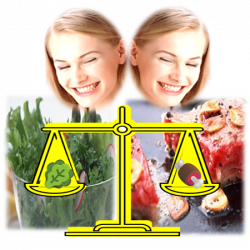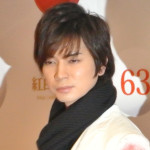「美味い!」の感覚は人類の“生き残り戦略”だった/元NHKアナ・中村克洋「人生を動かす“顔”パワー」講座:“晴顔”と健康⑥
今回は“顔のサイエンス”。「味」と「顔」の関係について科学が見つけた、興味深い“生き残りの戦略”をご紹介します。
■肉と野菜はどっちが美味(うま)い?それはなぜ?
生き物には生存のための本能が備わっています。これを“生き残りの戦略”と呼ぶことにしましょう。全ての生き物には、この戦略が活動の根源として働いています。そしてそれを実行する時には常に「ドーパミン」という快感ホルモンが噴き出し、“晴顔”が呼び起こされ「快楽を全身で感じる」ようにできています。
食事、睡眠、安全な住みか、などのほか子孫を残すための「生殖」や「育児」、食物を得るための「狩り」などたくさんの“生き残りの戦略”には必ず快楽が伴い、“晴顔”が呼び起こされるようセットされているのです。ヒトは、その快楽を追い求め、結果的に「生き残りの確率を高めている」のです。以下、味覚について見ていきましょう。
まず、“栄養価のとても高い”肉は、“とても美味い”と感じます。その一方で、“栄養価が低い”野菜などは、もちろん体にとって必要なものですが、個人差はあるものの、総じて、さほど美味いとは感じられないようになっているのです。
人間は、美味いと感じる「栄養価が高い食べ物」を、「優先的にたくさん摂る」 ことで、生き残りの確率を高めています。逆に、食べられないもの、食べたら害のあるものなど「生存を脅かすもの」は、“まずい”と感じて食べないのです。
■味だけではありません
この“生き残り戦略”は、「味覚」だけでなく「嗅覚」も強力に支配しています。ステーキの匂いに快感を感じ取り、食べたくなるのはおなじみの現象ですが、「ヒトは無意識のうちに現在自分に欠乏している栄養素の匂いを、敏感に感じ取り、それが猛烈に食べたくなる」というのです。2023年放送の「チコちゃんに叱られる!」(NHK)でもこのことは取り上げられていました。
たとえば「栄養不足」の場合は、肉などの「栄養価の高い食べ物の匂い」を最優先に感じ取って食べたくなり、ビタミン不足の場合、イチゴやレモンなど「ビタミンの多い食べ物の匂い」を優先して嗅ぎ取り、食べたくなる。しかもいったんその食べたくなった食物を食べた後は逆にその匂いに鈍感になってしまうというのです。実際、番組では、「スタッフがカレーを食べた後、目隠しをして、カレーを鼻の先まで近づけても、カレーだとは気がつかなかった」というリポートをしていました。生物における“生き残りの戦略” は徹底して、ムダがないようにできているのです。
■「おふくろの味」は、「0.9%」
もう一つ面白い例があります。「味噌汁の味」です。ヒトの血液の塩分濃度の最適値は0.9%ですから、ヒトが生き残るためには血液の塩分をこの濃度に保ち続けることが必要なのです。ですが、塩分はヒトの体内で作ることができません。そのため、塩味を「美味い」と感じてこれを取り込み、しかも濃度0.9%が、「一番美味い」と感じるよう味覚がセットしてあるのです。「料理」という手段をもつ唯一の生物であるヒトは、自分の血液の塩分濃度と同じ味つけをするよう“仕組まれている”と言ってもいいでしょう。そして塩分濃度が0.9%を超えると、ヒトはこれを辛すぎると感じてしまう。そのようにして、塩分を摂りすぎないようセットしてあるのです。
生き物には、「快楽を追い求め、不快を避ける」ように本能がセットされています。 そして、生き残るために必要なことは、必ず快楽を伴います。だから、生き物は本能に従ってさえいれば、結果として「生き残ることができる」 のです。
次回からは、「幸運を呼び込む“顔”のトリセツ」です。このシリーズもいよいよ佳境に入っていきます。
●プロフィール
なかむら・かつひろ1951年山口県岩国市生まれ。早稲田大学卒業後、NHK入局。「サンデースポーツ」「歴史誕生」「報道」「オリンピック」等のキャスターを務め、1996年から「ワイド!スクランブル」(テレビ朝日系)ほか、テレビ東京などでワイドショーを担当。日本作家クラブ会員。著書に「生き方はスポーツマインド」(角川書店)、「山田久志 優しさの配球、強さの制球」(海拓舎)、「逆境をチャンスにする発想と技術」(プレジデント社)、「言葉力による逆発想のススメ」(大学研究双書)などがある。講演 「“顔”とアナウンサー」「アナウンサーのストップ・ウォッチ“歴史館”」「ウィンウィン“説得術”」