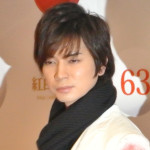青年の坂本龍馬像に会いにゆく/内田晃「ゆるゆる『歩き旅』のススメ!」
「三国志、竜馬がゆく、坂の上の雲。この3つの長編小説だけは、社会に出る前に読んでおけよ。絶対に損はしないから」
高校時代、ベテラン教師がオイラたちに熱く語ったことを今も覚えている。時代を超えて読み継がれる名作小説は、年齢や性別に関係なく“共通の話題と”なり、相手との距離を縮められる。実際に読んでおいて、大いに得したものだ。
その中でもハマったのが「竜馬がゆく」だ。主人公のモデルになった坂本龍馬の銅像を見るためだけに高知県、長崎県、鹿児島県を巡ったこともある。今回は久しぶりに龍馬像を目的に出かけてみた。
訪問先は東京都品川区の京浜急行本線立会川駅。出口を出て、商店街を左側に進むと北浜川児童遊園入口に龍馬像が建っていた。
懐手の肘を台にかける高知県・桂浜の銅像と同じポーズだが、どことなく違う印象を受ける。案内板を見ると“二十歳の龍馬像”とあり納得した。顔が若々しく、桂浜の像はブーツを履いていたが、こちらは草履を履いている。
ところで、なぜ龍馬像が立会川駅近くに建つのか。江戸期、この辺りに土佐藩の下屋敷があったからだ。その中には立会川河口の荷上場も入っていた。幕末、ペリー提督の黒船艦隊が来航すると、土佐藩は荷上場の沖に浜川砲台を築き江戸湾の警護に当たった。浜川砲台に詰めた藩士の中に若き龍馬がいたそうだ。
銅像から3分ほど歩いた新浜川公園には、浜川砲台に設置された大砲(ホーイッスル砲)のレプリカが置いてあると知り、足を運んでみた。ポカポカ日和の休日だったこともあり、草野球のユニフォーム姿のおじさんらが車座になり、缶ビール片手に談笑していた。
何やら、幕末の陽気な土佐藩士が警護の合間にくつろいでいるようで笑ってしまった。公園から勝島運河に出て、鮫洲駅へ向かう。運河には屋形船や釣り船が係留され、桜並木や花壇が両岸に続くことから“しながわ花海道と”も呼ばれている。サクラ、菜の花、ヒマワリ、コスモスなど、季節の花を愛でながらの花見さんぽも楽しそうだ。
鮫洲駅に到着。近くの大井公園脇にある山内豊信(容堂)の墓を訪ねた。幕末の四賢候に数えられる15代土佐藩主だ。最後の将軍・徳川慶喜に大政奉還を上申し、明治政府にも加わるが早々に辞任。大好きな酒を味わい尽くし46歳で他界した。号は鯨海酔侯。鯨のいる海の酔っ払い殿様という意味だ。
内田晃(うちだ・あきら):自転車での日本一周を機に旅行記者を志す。街道、古道、巡礼道、路地裏など〝歩き取材〟を得意とする。