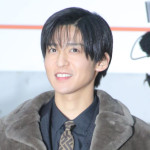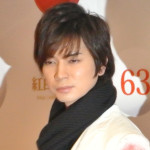野沢温泉の道祖神祭りへ(その②)/内田晃「ゆるゆる『歩き旅』のススメ!」
長野県・野沢温泉村で毎年1月15日に開催される「野沢温泉の道祖神祭り」に来ている。午後5時を過ぎるとすっかり暗くなり、大雪が降り出した。
「まずは初灯籠の出陣からです」と今回の案内役を務めてくれた山好きおじさん。初灯籠は約9メートルの中心柱に菱灯籠などを飾ったもので長男の誕生祝いに奉納される。その大きさから会場へは解体して運ばれる。
各部品を運ぶ奉納者の友人たちは“目出度く建てた命あるなら来年も〜”と道祖神の歌を歌いながら行進する。先導は大きな松明を掲げるが、重さのせいか出陣前の御神酒のせいか、少しふらつくのも祭りらしくてほほえましい。
次に案内されたのは採火処。厄年三夜講と25歳厄年の世話人が、火元の河野家主人にお焚き上げに使う元火をもらいに来るのだが、一筋縄ではいかない。三夜講と河野家が用意した合計10升の日本酒が酌み交わされ、覚悟の程を確かめられるのだ。1時間後、主人は許可を出すと烏帽子、白装束の姿に着替え、火打ち石を使って元火を起こす。
松明に移された元火とともに会場へ移動すると社殿の上には数え42歳の厄男、下には25歳の厄男が緊張の面持ちで待っていた。
社殿から100メートルほど離れた枯れ木の山に元火が移されるとクライマックスである“火の攻防戦”の始まりだ。麻を束ねた小さな松明に火をつけた村人が野沢組惣代、初灯籠の奉納者、子供、大人の順番で社殿を燃やそうとやって来る。これを42歳と25歳の厄男が防ぐ。特に最前線の25歳は大変で叩きつけられる松明を体で受け止め、社殿に移った火は松の枝で消す。
この日に用意された小さな松明は2000本。攻防戦は約1時間30分も続き、厄男は全員煤だらけだ。こう書くと酷いと感じる方もいるだろうが、現場に立てば“お前も大人だな。これからは大人の仲間だぞ”という村人からの手荒い祝福だとわかる。
攻防戦が終わり、双方で手締めをしたあとは社殿が燃やされ、初灯籠も投げ入れられる。約20メートルの火柱が立つ光景は圧巻だった。
翌日は社殿の熾火で餅を焼いて食べると1年間風邪を引かないとか。山好きおじさんと餅を焼いていると、厄男たちが片付け作業を始めた。誰もが顔に擦り傷や火傷を負っているが、どこか晴れやかで自信に満ちた表情をしている。
「野沢の男は道祖神祭りを経験して一人前になる」と山好きおじさんが語った言葉を思い出し、ニンマリとほほえんだ。
内田晃(うちだ・あきら):自転車での日本一周を機に旅行記者を志す。街道、古道、巡礼道、路地裏など〝歩き取材〟を得意とする。