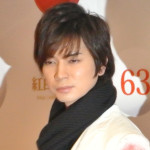徳川家康ごひいきの鷹場へ/内田晃「ゆるゆる『歩き旅』のススメ!」
天下人・徳川家康が夢中になった娯楽といえば鷹狩りだ。鷹狩りは訓練した鷹などを山野に放ち、野鳥や小動物を捕まえる狩猟術で、一説には生涯1000回以上も行ったという。
そんな家康が宿泊などに使う御殿を建てさせるほど、気に入っていた鷹場(狩場)の1つが埼玉県越谷市だ。その頃の越谷市は沼沢地が多く、たくさんの水鳥が棲息していた。1613年の鷹狩りでは1日に17羽の鶴を捕獲し、家康も上機嫌だったらしい。今回は家康の鷹狩りをキーワードに歩いてみよう。
東武スカイツリーライン越谷駅東口を出発して、旧日光街道を左に曲がる。見世蔵などが点在し越谷宿の面影が残る町並みを抜け、元荒川に出たら、橋を渡らずに右折して川沿いを進む。国道4号を横切り、さらに川沿いを進むと越ヶ谷御殿跡の石碑がある。
御殿は1604年に建てられ、徳川2代将軍の秀忠や4代将軍の家綱も訪れている。御殿の詳細は不明だが1657年の大火で江戸城が焼失した際に、仮の住まいとして江戸城二の丸に移されているので、立派な建物だったに違いない。
そのまま川沿いを歩き、宮前橋を渡った先には久伊豆神社が待つ。大国主命と言代主命(恵比寿様)を主祭神とする越谷の総鎮守であり、徳川将軍家からも篤く信仰された。
鎮守の森に続く長い参道や藤棚など、見どころは多いが、ひときわ目を引いたのが拝殿の狛犬だ。なんと! 麻ひもで足元がグルグル巻きにされている。
調べてみると“足止めの狛犬”といい、家出や悪所通い、多忙で家庭を顧みない家族がいる場合、このように祈願すると縁を結び直せるとか。外出ばかりの旅行記者にはちと耳が痛い。
ここから逆川緑道を歩き林泉寺へ。本堂前に立つ高さ10メートルほどのマキの木は家康が鷹狩りの際に愛馬の手綱を繋いだと伝わり“駒止のマキ”と呼ばれている。今は枯れてしまったが、家康が参拝時に手を洗い、口をすすいだという権現井戸跡と記念碑もあった。
さらに40分ほど歩いて大聖寺を訪問。750年に創建した越谷最古の寺といわれ、家康は越ヶ谷御殿の建設前に宿泊している。その謝礼に夜具(寝間着)や湯呑みなどを贈っている。
参拝後、元荒川沿いを30分ほど歩くと越谷駅に到着だ。万歩計を見ると1万5000歩を突破している。家康は鷹狩りがいい運動になり健康維持に役立つとしていたが、ゆるゆる歩き旅も同じことが言えそうだ。
内田晃(うちだ・あきら):自転車での日本一周を機に旅行記者を志す。街道、古道、巡礼道、路地裏など〝歩き取材〟を得意とする。